| 「エートス」こいて、もぉ〜!トップへ
|
Net-Sproutトップへ |
ディスカバー・アメリカ〜必殺のアメリカ史発見! 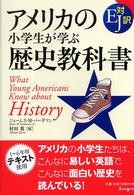
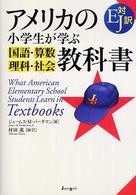
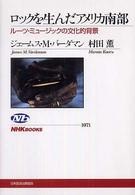
|
|
http://www.net-sprout.com/iitaihoudai/062sekaishi.html http://www.net-sprout.com/iitaihoudai/063sekaishi.html |
||
|
「・・・それからもう一つ、かねがね世界史の教え方で疑問を持っていたことがある。それは、現在の日本に最も影響を与える2つの大国、アメリカと中国についての勉強の比重が、欧州史に較べて相対的に低いことである。 少なくとも、僕らの世代(1960年代から70年代にかけて高校生活を送った世代)においてはそうだった。中国に関しては、確かに、殷・周の時代から秦・漢・隋・唐・・と学んでいって、その比率は低くはない。だが、肝腎の清朝末期から日華事変、満州建国から、戦後の社会主義国家建設にいたる、最新中国史の勉強は少なかった。 アメリカ建国の歴史にしても、大学受験での出題が少ないとかの理由でおざなりだったように記憶する。南北戦争の起こった理由を正確に言える僕の同世代人は少ない筈だ。・・・・」 と書いた。 |
||
|
この本は、バージニア大学の「E.D.ハーシュ」という英文学の教授が編集した6冊の小学生用教科書からアメリカ史の部分だけを、早稲田大学教授の「ジェームズ・M・バーダマン」氏が抜粋して一冊にまとめたものを同じく早稲田大学教授の「村田薫」氏が翻訳したものである。なぜ、文学の批評理論を専門とするハーシュ教授がアメリカの小学生用の教科書を作ったのかというと・・・。 |
||
|
6冊のテキストの英語のレベルは、学年を追うごとに徐々に難しくなっていきます。アメリカ史の章は1年、2年では歴史上有名なエピソードが紹介され、通史は3年からとなっています。本書は3年生の教科書から取った文章で始まり、第5章の「第1次世界大戦」以降が6年生用のものです。1年、2年用教科書で必要な箇所は、適宜各時代の章の中に織り込みました。」(前書きより抜粋) |
||
|
第1章 アメリカ発見から植民地まで 第2章 独立戦争と新国家 第3章 南北戦争と南部再建 第4章 西部への拡大とフロンティア 第5章 第1次世界大戦と大恐慌 第6章 第二次世界大戦と冷戦 第7章 ‘60年代の大変動 目次は上記のとおりだが、ところどころにあるコラムのうち主なタイトルを以下に列挙する。 |
||
|
「セイレムの魔女裁判」 「ダニエル・ブーン」 「ポール・リビア」 「ヤンキー・ドウードル」 「ベンジャミン・フランクリン」 「トマス・ジェファーソン」 「国歌 “星条旗”」 「マニフェスト・デスティニー」 「アラモ砦とディビー・クロケット」 「ハリエット・ダブマン」 「黒人霊歌」 「サムター砦と南北戦争の始まり」 「南北戦争か市民戦争か」 「グラントとリー」 「Ku Klux Klanの出現」 「チェロキー文字と“涙の道”」 「自由の女神」 「リンドバーグとエアハート」 「狂乱の‘20年代」 「エレノア・ルーズベルト」 「ジャッキー・ロビンソン」 「マルコムX」 「ウッドストック世代」 「月面着陸とフロンティア」 如何であろうか?先程の目次では「そんなもんフツー」と思われた方も「ムムムム・・・」と興味を持たれたのではないだろうか? |
||
|
僕は、アメリカ、とくにアメリカ中南西部の音楽が大好きだ。僕は英語は苦手なのだが、その歌詞にはおおいに興味がある。特に、頻出する、おそらくアメリカの歴史に大きく関わっていて、アメリカ人なら常識なんだろうな、と想像はつくものの、それが何なのかはわからなったキーワードについて、今回、「えっ、そういうことかいな」という「目から鱗」現象がいくつもあった。 読者の方々にもアメリカ音楽好きが多いと思うけど、みなさん、これを読むと理解が深まりますよ! |
||
|
http://www.net-sprout.com/iitaihoudai/068nanbu.html そもそもは「アメリカ南部」というそのものズバリのタイトルの講談社新書の作者であるのだが、日記でふれている「ロックを生んだアメリカ南部〜ルーツ・ミュージックの文化的背景」(写真右)という名著に接し、その他の著作をアマゾンで検索していてめっけたのである。そのタイトルを見て、ビビっと来て早速購入!見事にビンゴ! 実はこのとき、同様の企画意図で編まれた「アメリカの小学生が学ぶ国語・算数・理科・社会の教科書」(写真中)という姉妹書も一緒に購入したのだが、こちらも、本書に劣らずアメリカ(とりわけ僕のようにアメリカ音楽の歌詞に興味ある方!)への理解への力強い味方となる事請け合いの必携の好著である。 |
||
|
「英語で苦しんだ経験のある方なら、日本語を勉強している外国人に向かって、「春はあけぼの・・・」とか、「勝てば官軍」、あるいは「財布には一葉も諭吉もない」などとは言ったりはしないでしょう。これは少し極端な例だとしても、この逆の事態を英語で経験することはよくあって、私達の思考や舌に急ブレーキがかかります。それは熟語とか会話の決まり文句の問題ではなく、その英語の文章や会話がふまえている背景的な知識を共有していないがために起こるトラブルです。文化とは特定の集団や民族においてのみ通用するものと司馬遼太郎は定義しました。ということは、他国の文化はつねに異文化であるわけですが、その異文化が共通認識として持つ知識を学ばなければその言語の習得も難しくなります。 中略 ・・・というと、いかにも堅苦しいお勉強の本のように聞えますが、原著の「シリーズ」には「へぇ〜」「なるほど」「あはは」が、巧みに整理・配列されていて、アメリカの小学生の知的冒険の旅への欲求に十分こたえています。 中略 ・・・マザーグース、言葉遊び、世界の宗教、ことわざ、ギリシャ神話・叙事詩、アーサー王物語、演説、文学の基本、地理、そして算数や理科?こうした英語国民の血脈にあたる知識をおざなりにするわけにはいきません。 中略 ・・・物語やことわざばかりでなく、直喩・暗喩などの技法にも独特の生命力やキャラクターがあって、時の流れを乗り切ってきたのも納得できます。おそらくローマ数字や幾何学でさえ例外ではありません。いわばどの知識にも「顔かたち」があって、人間のジタバタにつきあいながら歴史の時空間を悠々と歩き続けているとでもいった感じです。 長い時を生き延びてきた彼らの会釈に応えて、じっくり耳を傾けてみてはいかがでしょうか」 |
||
|
|
||
|
だが、「教育再生会議」なるまったくあほらしい非再生的な会議体しかもてない本邦と違い、アメリカは本当の危機に直面するとこういう根本からの修正を短期間にやりとげる底力があることに驚く。つくづく奇妙な国である。 |
||
|
|
||
| 「エートス」こいて、もぉ〜!トップへ
|
Net-Sproutトップへ |