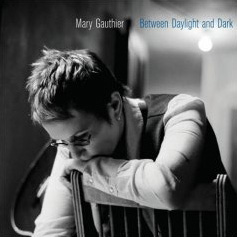|
 |
 |
太鼓もやっぱり皮がうまい!
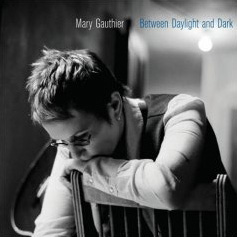




|
 アリー・ゴウシェの新作「Between Day and Dark」を聴く!実はハワイへ行く前日に入手し、成田までの車中で聴くつもりだったのだが、同行する友人が車にあったニック・ロウの新作「AT MY AGE」を目ざとく見つけ出し、「あっ!これ、まだ聴いてないんですよ!聴いていいですかぁ?」「えっ!どうじょ!どうじょ!」ということになり、結局帰国後の成田から自宅までの帰路で聴くこととなる。(帰りは一人だったのである) アリー・ゴウシェの新作「Between Day and Dark」を聴く!実はハワイへ行く前日に入手し、成田までの車中で聴くつもりだったのだが、同行する友人が車にあったニック・ロウの新作「AT MY AGE」を目ざとく見つけ出し、「あっ!これ、まだ聴いてないんですよ!聴いていいですかぁ?」「えっ!どうじょ!どうじょ!」ということになり、結局帰国後の成田から自宅までの帰路で聴くこととなる。(帰りは一人だったのである)
|
 |
 |
 曲目、「ドゥゥゥェェ〜〜ン」という、ものすごく皮鳴りの良い太鼓の音で幕が開く。続けていつも通りの、やさぐれて、ささくれだったメアリーの歌声が届けられると、あっという間に10曲を聴了!う〜〜〜ん、素晴らしいサウンド!でも前2作とはあきらかに何かが違うのだ。これまでの、メアリーの剥き出しの孤独感、うっかり触れば指が吹っ飛びそうな切迫感が上手にマスキングされている。血糊のついていた抜き身の刀身が、精緻な象眼がほどこされ、ところどころにモノクロームな静かな光を放つ螺鈿が埋め込まれた美しい半透明の鞘に収まっている・・・・でもその鞘を通してでもやはりメアリーの救われない孤独が、タイトル通りの薄暮の中に静かに浮かび上がってくる・・・とでも言えばいいのだろうか。 曲目、「ドゥゥゥェェ〜〜ン」という、ものすごく皮鳴りの良い太鼓の音で幕が開く。続けていつも通りの、やさぐれて、ささくれだったメアリーの歌声が届けられると、あっという間に10曲を聴了!う〜〜〜ん、素晴らしいサウンド!でも前2作とはあきらかに何かが違うのだ。これまでの、メアリーの剥き出しの孤独感、うっかり触れば指が吹っ飛びそうな切迫感が上手にマスキングされている。血糊のついていた抜き身の刀身が、精緻な象眼がほどこされ、ところどころにモノクロームな静かな光を放つ螺鈿が埋め込まれた美しい半透明の鞘に収まっている・・・・でもその鞘を通してでもやはりメアリーの救われない孤独が、タイトル通りの薄暮の中に静かに浮かび上がってくる・・・とでも言えばいいのだろうか。
|
 アリーは、捨て子で、養子に出され、15才で両親の車を盗んで学校を抜け出して捕まり刑務所に収監。出所後、ドラッグ漬けとなるが薬物療養所で更正し(そこまでの前半生が、2枚目のアルバム「ドラッグクィーン イン リムジン」で自伝的に歌われている)、哲学を学びに大学へ。その後料理学校に行って、レストラン(ボストン初のケイジャンレストラン、その名は“DIXIE KITCHEN”(もちろん彼女はロウェル・ジョージの大ファンである)を経営して成功。35才から音楽を始め、そのお店の権利金を売ったお金で自主制作のアルバムを2枚制作、しかもレズビアンという波瀾万丈の人だ。確かに悲惨な前半生ではある。だがそんな人生はたくさんあるし、地球規模で見渡せば、彼女以上に凄惨な人生は、そこらじゅうに転がっている。 アリーは、捨て子で、養子に出され、15才で両親の車を盗んで学校を抜け出して捕まり刑務所に収監。出所後、ドラッグ漬けとなるが薬物療養所で更正し(そこまでの前半生が、2枚目のアルバム「ドラッグクィーン イン リムジン」で自伝的に歌われている)、哲学を学びに大学へ。その後料理学校に行って、レストラン(ボストン初のケイジャンレストラン、その名は“DIXIE KITCHEN”(もちろん彼女はロウェル・ジョージの大ファンである)を経営して成功。35才から音楽を始め、そのお店の権利金を売ったお金で自主制作のアルバムを2枚制作、しかもレズビアンという波瀾万丈の人だ。確かに悲惨な前半生ではある。だがそんな人生はたくさんあるし、地球規模で見渡せば、彼女以上に凄惨な人生は、そこらじゅうに転がっている。
|
 |
 |
 は以前このブログに「音楽の4つの“化”と音楽著作権使用料」と題した文章の中にこういうことを書いたことがある... は以前このブログに「音楽の4つの“化”と音楽著作権使用料」と題した文章の中にこういうことを書いたことがある...
|
 何も、音楽家だけが、格別ドラマチックな人生を送っているわけではない。普通に暮らしている人にもアンビリーバボーなことは普段におきる。身内の病気だったり、恋人の裏切りだったり、親友の自殺だったり・・ 何も、音楽家だけが、格別ドラマチックな人生を送っているわけではない。普通に暮らしている人にもアンビリーバボーなことは普段におきる。身内の病気だったり、恋人の裏切りだったり、親友の自殺だったり・・
|
 |
 |
 争時のイラクでは、ふつうに暮らしている人の民家の屋根を突き破って爆弾が落ちてくる・・・生きていれば、"事実は小説より奇なり"みたいなことはそこら中にある。たまたま、音楽ができる人におこったその音楽家固有の出来事・・それは、本人にとっては、死ぬほどつらいできごとだったり、ドロだらけのおにぎりを口に押し込められるような、あるいは泥水をむりやり飲まされるよう体験でも・・それを「死ぬほどつらい」とか「どろのおにぎりだ」とか「泥水だ」とストレートに言ってしまえば、その人だけの極めて限定された個人的体験として完結するしかないが、その音楽家が一旦飲み込んだイタくて苦い「個人的」体験が、そのからだとこころを通して音楽を媒介にして表現された作品は、濾過され純化され浄化されている。だから、本人にとっては泥水であったものが、その音楽家の作品を聴く人にとっては、文字通り、のどの渇きを癒す、浄水へと昇華する。それだけではない。単に水道に取り付ける浄水器と違い、天然に濾過された水・・ボルビック、ヴィッテル、ペリエ、などにはミネラルや自然の炭酸まで入っていて、我々を健康にしてくれるばかりか、その味の違いが楽しみを与えてもくれるのと同じように、異なる音楽家の様々な作品が我々の多様な嗜好に対応しくれる。 争時のイラクでは、ふつうに暮らしている人の民家の屋根を突き破って爆弾が落ちてくる・・・生きていれば、"事実は小説より奇なり"みたいなことはそこら中にある。たまたま、音楽ができる人におこったその音楽家固有の出来事・・それは、本人にとっては、死ぬほどつらいできごとだったり、ドロだらけのおにぎりを口に押し込められるような、あるいは泥水をむりやり飲まされるよう体験でも・・それを「死ぬほどつらい」とか「どろのおにぎりだ」とか「泥水だ」とストレートに言ってしまえば、その人だけの極めて限定された個人的体験として完結するしかないが、その音楽家が一旦飲み込んだイタくて苦い「個人的」体験が、そのからだとこころを通して音楽を媒介にして表現された作品は、濾過され純化され浄化されている。だから、本人にとっては泥水であったものが、その音楽家の作品を聴く人にとっては、文字通り、のどの渇きを癒す、浄水へと昇華する。それだけではない。単に水道に取り付ける浄水器と違い、天然に濾過された水・・ボルビック、ヴィッテル、ペリエ、などにはミネラルや自然の炭酸まで入っていて、我々を健康にしてくれるばかりか、その味の違いが楽しみを与えてもくれるのと同じように、異なる音楽家の様々な作品が我々の多様な嗜好に対応しくれる。
|
 過、浄化、純化、昇華・・これを音楽の「4か」という。(えっ!
聞いてない!・・わかってます!だって今日はじめて言ったんだから・・) 過、浄化、純化、昇華・・これを音楽の「4か」という。(えっ!
聞いてない!・・わかってます!だって今日はじめて言ったんだから・・)
砂漠のオアシス、干天の慈雨・・それらに感謝しない人はいないだろう。その感謝の気持ち・・それが音楽家に対するリスペクトであり、実は著作権使用料を支払うというのは、この感謝の気持ちを金銭に置き換える行為のことなのだ。“
|
 |
 |
 は、それらの濾過、浄化、純化、昇華された音楽の中でもとりわけ、死臭ではなく、死の影の匂いを感じさせる(つまり影には匂いはないのに、そんな有りえない匂いを感じさせる)音楽を愛好する、徹頭徹尾!まるで無味無臭なもの、あるいは濾過されていない、そんな音楽を愛好しない、徹頭徹尾! は、それらの濾過、浄化、純化、昇華された音楽の中でもとりわけ、死臭ではなく、死の影の匂いを感じさせる(つまり影には匂いはないのに、そんな有りえない匂いを感じさせる)音楽を愛好する、徹頭徹尾!まるで無味無臭なもの、あるいは濾過されていない、そんな音楽を愛好しない、徹頭徹尾!
|
 は今回、これまでのガーフ・モリックスのプロデュースからジョー・ヘンリーに変わっている。おー!ガーフ!またもやルシンダの二の舞いかい?なんで、君はそういう運命なの! は今回、これまでのガーフ・モリックスのプロデュースからジョー・ヘンリーに変わっている。おー!ガーフ!またもやルシンダの二の舞いかい?なんで、君はそういう運命なの!
「糟糠の妻」という言葉がある。差し詰め、ガーフはルシンダ・ウィリアムスの糟糠の妻であり、中興の祖である。またメアリー・ゴウシェにおいても同様だった。
|
 |
 |
 が、芸能界でも、まだ売れない時代からタレントを支えた続けた女性が、そのタレントがブレイクした瞬間、新たな彼女(大抵は若い!)を作られて離別される、なんてことが日常茶メシだが、ガーフ・モリックスもどうやらそういう運命にあるようだ。まことに哀しき男であるが、今年の5月、彼のライブを新中野のライブハウス「弁天」で聴いたときはジーンと感動してしまった。間合いとうかテンポが地上的でない。どこまでも天国的なタイムレスなタイム感である。そして視線の先にこの世のものが何も映っていない乾いた哀しみに文句なく泣けた。ついでに観客のあまりの少なさにも文句ありで泣けた。このときベースを担当した安部王子に聞いたのだが、ガーフが一番長く一緒にライブをやっていたのはなんと故ウォーレン・ジヴォンだそうである!なるほど!これまた地球のリズムでなく、最後は宇宙の果てを見つめていたミュージシャンではないか。僕はガーフにもウォーレン・ジヴォンにも死の影の匂いを強く感じる。そしてそれはルシンダウィリアムにも、メアリー・ゴウシェにも感じることだった。だからガーフのプロデュースは彼女たちにピッタリだと思っていたのである。かなり前のことだが、たまたま飲み屋の女性二人と映画の話をしていたとき「どうして、男はあんなに戦争映画がすきなのか、さっぱりわからない!」と言われたので、男は「どうやって死ぬか」という大きな命題を与えられているからかも、といったのだが、彼女らには「???」であった。男は、死ぬほど「死」が怖いのに、死ぬほど「死」にあこがれる。このリストラ時代に「自殺する」お父さんが増えているが、「女」はそう簡単に死なない。「死」について興味がないからだ。「生む」装置を備えて「生まれてきた」女性が「死」に興味を持たないように作られているのは当たり前かも知れない。「女性」という「性」は「とにかく生きよう」とする「性」であるのに対して「男性」という「性」は「とにかく死のう」とする「性」である。“エロス”と“タナトス”に置き換えることもできる。だから、知らず知らず死の淵に引きずり込むようなガーフのプロデュースからいつか逃れようという作用が女性に働くのではないか?反対にウォーレンは文字通り死の直前までガーフと一緒にいた。 が、芸能界でも、まだ売れない時代からタレントを支えた続けた女性が、そのタレントがブレイクした瞬間、新たな彼女(大抵は若い!)を作られて離別される、なんてことが日常茶メシだが、ガーフ・モリックスもどうやらそういう運命にあるようだ。まことに哀しき男であるが、今年の5月、彼のライブを新中野のライブハウス「弁天」で聴いたときはジーンと感動してしまった。間合いとうかテンポが地上的でない。どこまでも天国的なタイムレスなタイム感である。そして視線の先にこの世のものが何も映っていない乾いた哀しみに文句なく泣けた。ついでに観客のあまりの少なさにも文句ありで泣けた。このときベースを担当した安部王子に聞いたのだが、ガーフが一番長く一緒にライブをやっていたのはなんと故ウォーレン・ジヴォンだそうである!なるほど!これまた地球のリズムでなく、最後は宇宙の果てを見つめていたミュージシャンではないか。僕はガーフにもウォーレン・ジヴォンにも死の影の匂いを強く感じる。そしてそれはルシンダウィリアムにも、メアリー・ゴウシェにも感じることだった。だからガーフのプロデュースは彼女たちにピッタリだと思っていたのである。かなり前のことだが、たまたま飲み屋の女性二人と映画の話をしていたとき「どうして、男はあんなに戦争映画がすきなのか、さっぱりわからない!」と言われたので、男は「どうやって死ぬか」という大きな命題を与えられているからかも、といったのだが、彼女らには「???」であった。男は、死ぬほど「死」が怖いのに、死ぬほど「死」にあこがれる。このリストラ時代に「自殺する」お父さんが増えているが、「女」はそう簡単に死なない。「死」について興味がないからだ。「生む」装置を備えて「生まれてきた」女性が「死」に興味を持たないように作られているのは当たり前かも知れない。「女性」という「性」は「とにかく生きよう」とする「性」であるのに対して「男性」という「性」は「とにかく死のう」とする「性」である。“エロス”と“タナトス”に置き換えることもできる。だから、知らず知らず死の淵に引きずり込むようなガーフのプロデュースからいつか逃れようという作用が女性に働くのではないか?反対にウォーレンは文字通り死の直前までガーフと一緒にいた。
|
 ーフの最新作「ダイヤモンド・トゥ・ダスト」(DIAMONDS TO DUST)のテーマは、ジャケットにモチーフとして用いられている「白化した骨」である(真ん中の写真は、今年行われたガーフの日本公演用ポスターだが、彼の胸ポケットからのぞいているのは、”白化した骨”である)。その歌は、文字通り、” 朝には紅顔であっても ”結局は何も残すことなく“ 夕べには白骨となる男性 ”性”への挽歌であり、その4曲目「BLANCKET」は、ずばりそのウォーレン・ジヴォンに捧げられている。そして1曲だけカバーされているのがボブ・ディランの「WITH GOD ON OUR SIDE」・・・両曲とも思わずこうべを垂れてききこんでしまう絶唱だ。この絶唱を聞いて涙を流さない男はがいたらお目にかかりたい・・いや、お目にかかりたくない。ドラムのリック・リチャーズとハモニカのレイ・”骨”ヴィル(ちがった!ボネヴィル)、そしてコーラスのパッツィ・グリフィン以外のすべての楽器はガーフが担当しているが、全編に哀しみが白化し氷結した「氷の世界」である。安藤広重に「蒲原」という氷雪の世界が描かれた浮世絵がある(写真右)が、あの絵の中で菅笠をおさえながら深々と降り積む雪の中を進む男がいるが、それはガーフ・モリックスその人である。 ーフの最新作「ダイヤモンド・トゥ・ダスト」(DIAMONDS TO DUST)のテーマは、ジャケットにモチーフとして用いられている「白化した骨」である(真ん中の写真は、今年行われたガーフの日本公演用ポスターだが、彼の胸ポケットからのぞいているのは、”白化した骨”である)。その歌は、文字通り、” 朝には紅顔であっても ”結局は何も残すことなく“ 夕べには白骨となる男性 ”性”への挽歌であり、その4曲目「BLANCKET」は、ずばりそのウォーレン・ジヴォンに捧げられている。そして1曲だけカバーされているのがボブ・ディランの「WITH GOD ON OUR SIDE」・・・両曲とも思わずこうべを垂れてききこんでしまう絶唱だ。この絶唱を聞いて涙を流さない男はがいたらお目にかかりたい・・いや、お目にかかりたくない。ドラムのリック・リチャーズとハモニカのレイ・”骨”ヴィル(ちがった!ボネヴィル)、そしてコーラスのパッツィ・グリフィン以外のすべての楽器はガーフが担当しているが、全編に哀しみが白化し氷結した「氷の世界」である。安藤広重に「蒲原」という氷雪の世界が描かれた浮世絵がある(写真右)が、あの絵の中で菅笠をおさえながら深々と降り積む雪の中を進む男がいるが、それはガーフ・モリックスその人である。
|
 |
 |
 、今回のジョー・ヘンリー・・・こちらは逆にキラキラ輝く明るい才能の塊のような人である。みずからのソロワークもここ数年素晴らしい充実ぶりであるが、プロデュースワークも猖獗を極めている。2002年にはソロモン・バークスの「DON‘T GIVE UP ON ME」,2005年にはメーヴィス・ステイプルやアラン・トゥーサン等をフィーチャーした素晴らしいソウルアルバム「BELIEVE TO MY SOUL」をプロデュースしているし、エイミー・マン、アーニー・ディフランコ、エルヴィス・コステロの新作まで、まさに旭日大将軍のごとき日の出の勢いである。ガーフのように一瞬の孤独を切り取って宙吊りに置くようなプロデュースではなく、実に丁寧に作り込まれているが、決してオーバープロデュースはない。「ガーフの世界」が豪快に飲むことだけを目的とした荒々しい男酒だとすれば、こちらは最初から品評会でゴールドメダルを狙って丹念に作られた吟醸酒の如き女酒である。 、今回のジョー・ヘンリー・・・こちらは逆にキラキラ輝く明るい才能の塊のような人である。みずからのソロワークもここ数年素晴らしい充実ぶりであるが、プロデュースワークも猖獗を極めている。2002年にはソロモン・バークスの「DON‘T GIVE UP ON ME」,2005年にはメーヴィス・ステイプルやアラン・トゥーサン等をフィーチャーした素晴らしいソウルアルバム「BELIEVE TO MY SOUL」をプロデュースしているし、エイミー・マン、アーニー・ディフランコ、エルヴィス・コステロの新作まで、まさに旭日大将軍のごとき日の出の勢いである。ガーフのように一瞬の孤独を切り取って宙吊りに置くようなプロデュースではなく、実に丁寧に作り込まれているが、決してオーバープロデュースはない。「ガーフの世界」が豪快に飲むことだけを目的とした荒々しい男酒だとすれば、こちらは最初から品評会でゴールドメダルを狙って丹念に作られた吟醸酒の如き女酒である。
|
 して、この一連のジョー・ヘンリーの音楽活動を一手に引き受けている感が有るのが、ドラムのジェイ・ベレローズとベースのデーヴィッド・ピルチのリズム隊である。ジェイとデーヴィッドと言えば、そう「マデリン・ペルー」の「ハーフ・ザ・パーフェクト」のコンビではないか!その時も思ったが、ジェイのドラムはスティックよりマレットを多用し、実に豊かな音色を感じさせてくれる。ドラムはリズム楽器とばかり思っていたが、まるで荘厳なゴシック建築の巨大な伽藍の中を吹き抜ける風のように色彩豊かな音色楽器だったのである。そしてジョー・ヘンリーが設計したその巨大伽藍の「ベース」メントをデヴィッド・ピルチが支える構図となっている。 して、この一連のジョー・ヘンリーの音楽活動を一手に引き受けている感が有るのが、ドラムのジェイ・ベレローズとベースのデーヴィッド・ピルチのリズム隊である。ジェイとデーヴィッドと言えば、そう「マデリン・ペルー」の「ハーフ・ザ・パーフェクト」のコンビではないか!その時も思ったが、ジェイのドラムはスティックよりマレットを多用し、実に豊かな音色を感じさせてくれる。ドラムはリズム楽器とばかり思っていたが、まるで荘厳なゴシック建築の巨大な伽藍の中を吹き抜ける風のように色彩豊かな音色楽器だったのである。そしてジョー・ヘンリーが設計したその巨大伽藍の「ベース」メントをデヴィッド・ピルチが支える構図となっている。
|
 |
 |
 くところによると、ジェイは太鼓の皮の上に更に別のケモノの皮をかぶせて叩くとか、和太鼓をドラムセットに組み入れたり、戦前のライブハウスに捨てられていた太鼓をレストアして使用するんだそうである。そうだよなぁ、何もドラムセットはこうでなければならぬ、なんてことは何もないんだもんな。誠に自由で、その皮鳴りが、聴く者の心に実によく「響く」ドラムである。 くところによると、ジェイは太鼓の皮の上に更に別のケモノの皮をかぶせて叩くとか、和太鼓をドラムセットに組み入れたり、戦前のライブハウスに捨てられていた太鼓をレストアして使用するんだそうである。そうだよなぁ、何もドラムセットはこうでなければならぬ、なんてことは何もないんだもんな。誠に自由で、その皮鳴りが、聴く者の心に実によく「響く」ドラムである。
|
 のジェイのドラムが心地よく響く5曲目「Before you
leave」は、絶品のバラード!サビで裏返るメアリーの声の何と切ないこと! のジェイのドラムが心地よく響く5曲目「Before you
leave」は、絶品のバラード!サビで裏返るメアリーの声の何と切ないこと!
表題曲である3曲目の「Between Daylight and Dark」はサビあとのピアノで弾かれるワルツが世にも切なくて美しい。
また2曲目「Can‘t find way」はメアリーの故郷ルイジアナを襲ったカトリーナ台風の悲劇と絶望を歌っているが、そこには明日への希望を聞き取ることができる。この曲でもドラムがその希望を伝えるのに大きな役割を果たしている。
|
 |
 |
 は小さいときから甘いものがだめで、お饅頭も皮だけ食べて中のアンコを残して家人に怒られていた。またオハギも上のアンコを取って、やはりゴハンだけ食べて怒られていたが、なんだ!やっぱりドラムも皮がオイシイんじゃん! は小さいときから甘いものがだめで、お饅頭も皮だけ食べて中のアンコを残して家人に怒られていた。またオハギも上のアンコを取って、やはりゴハンだけ食べて怒られていたが、なんだ!やっぱりドラムも皮がオイシイんじゃん!
|